詳細プロフィールはココ YouTube はじめました
最新記事 by Ayaka (全て見る)
※コンテンツの無断転載禁止(リンク歓迎)
.

◆ポーランド語:Kazimierz Dolny
カジミエシュ・ドルニ(正確には〜ドルヌィの発音が近い)はポーランドの東側にある小さな街。起源は11世紀にさかのぼり、やがてポーランド王国の重要な貿易都市となります。14世紀半ばの国王カジミエシュ3世が当時の首都クラクフ郊外にカジミエシュを建設すると、カジミエシュ・ドルニと呼ばれるようになりました。繁栄は16世紀末頃までつづき、それ以降は衰退するも19世紀末には観光地化。今日では芸術の町として知られます。


.
カジミエシュ・ドルニの歴史

11世紀頃、のちのカジミエシュ・ドルニとなる周辺にヴィエトジュナ・グラという集落があった。1170年頃、カジミエシュ2世はカトリック修道女にいくつかの村を建設して与え、彼の名を取って「カジミエシュ」と名付けられた。カジミエシュという名が文献に初めて登場したのは1249年である。
◆カジミエシュ2世…在位1177〜1190年のポーランド大公。当時のポーランドには国王がおらず、大公が国家の君主であった。
ヴワディスワフ・ウオキェテクの治世、カジミエシュ2世の代に築かれた石造りの防御塔がパワーアップ。ヴィスワ川の交易路に沿って建てられ、初期の要塞となる。その後、カジミエシュ3世は外側にあった街を王立都市として定め、城や教会に資金提供。貿易都市としての発展に大いに貢献した。
◆ヴワディスワフ・ウオキェテク…在位1320〜1333年のポーランド国王。分裂していたポーランド国家を再統合した。死後、息子カジミエシュ3世が跡を継ぐ。
◆カジミエシュ3世…在位1333〜1370年。ピャスト朝最後の国王であり、ポーランドの司法制度を整え、93の新しい都市を建設した。
スウェーデンとの戦争が始まり、町は急激に衰退。破壊されたカジミエシュを再建するため、国王ヤン3世ソビエスキはカジミエシュのユダヤ人に商業特権を与えた。ユダヤ人商人によって少しの繁栄を取り戻すも18世紀初頭、疫病により住民の多くが死亡。城に隣接する丘に3つの十字架が建てられた。
スウェーデン軍はポーランドの主要都市を次々と攻め、破壊と略奪を繰り返した。人口も一気に減少。そこで国王ヤン3世ソビエスキ(在位1674〜1696年)はアルメニア人やユダヤ人をカジミエシュに移住させるが、かつての繁栄を取り戻すことはできなかった。
隣国の政治干渉が著しくなった1770年頃、国王スタニスワフ・アウグストはカジミエシュのユダヤ人に平等権を与える。ユダヤ人が町の土地を購入し、そこに家を建て、自由に取引することを許可した。しかし1795年の第3次ポーランド分割の結果、ヴィスワ川の交易も途絶え、復興が遠のく。
◆スタニスワフ・アウグスト…ポーランド・リトアニア共和国の最後の国王。在位1764〜1795年。ポーランドが消えるまで手を尽くすも国家を救うことはできなかった。
自由と独立を求めるポーランド人の蜂起が起こるも失敗し、皇帝により市の権利も剥奪された。以降、ポーランドの歴史家や考古学者による研究対象となり、またカジミエシュの建築や芸術に関心を持ったアーティストや歴史愛好家が集まるようになる。19世紀末以降は夏のリゾート地となった。
19世紀、ルブリンに住む大富豪がヴィスワ川を望む美しいカジミエシュに注目し、プールや別荘を建設。やがてポーランド有数の保養地となり、富裕層が多く訪れるようになった。
戦争ではロシア軍によってカジミエシュの大部分が破壊されたが、戦後、123年を経て独立したポーランド共和国のもとで復興が始まる。1923年夏、ワルシャワ美術学校の教授と学生がカジミエシュを訪れ、芸術の村というイメージを定着させた。今日までカジミエシュには多くの芸術家が訪れる。
古代遺跡のような塔と城にインスピレーションを受け、多くのアーティストがカジミエシュ・ドルニを舞台とした作品を書いている。
カジミエシュ・ドルニの古城

この小さな街のシンボルは小高い丘に建つ古城。初期の要塞は12世紀から存在し、城としての言及は1359年の文献に見られます。この頃、国王カジミエシュ3世の資金提供により高さ7mの城壁が建てられ、南側の上階は2つの居住スペースに繋がっており、四角い塔が隣接していました。
15世紀には北東に拡大され、礼拝堂が備わった塔が南西に増築されます。15世紀末から16世紀にかけては中庭が水平になり、上階の居住スペースは地下となり、建物全体が高くなりました。1509年から1644年までは中貴族のフィルレイ家が所有し、城の拡張は17世紀前半まで続いています。
1655年、街はスウェーデン軍による破壊・略奪を受け、一時はスウェーデン王が城に住んでいました。18世紀に城の再建が行われ、1707年にはロシア皇帝のピョートル大帝が訪れています。しかし北方戦争(バルト海域の覇権をめぐって行われたスウェーデンとロシアとの戦争)により城はまたもや破壊され、ポーランド分割中に起こったロシアとの戦争で遺跡と化しました。19世紀以降は歴史的記念物として認識されはじめ、第一次世界大戦前には隣接する塔を含めた城の保護作業が実施されます。小高い丘に建つ白い古城とルブリンの建築要素は芸術家を魅了し、物語の舞台にもなりました。
.
 Copyright secured by Digiprove © 2016-2021
Copyright secured by Digiprove © 2016-2021




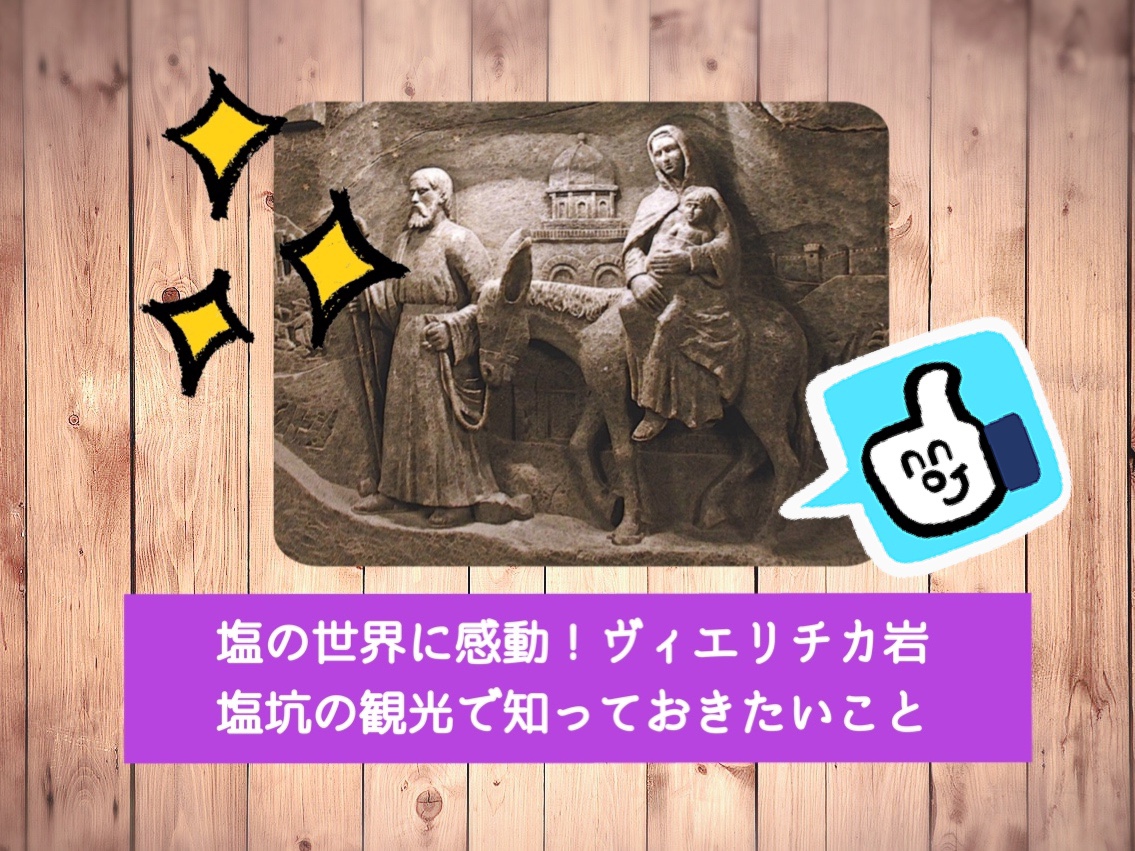




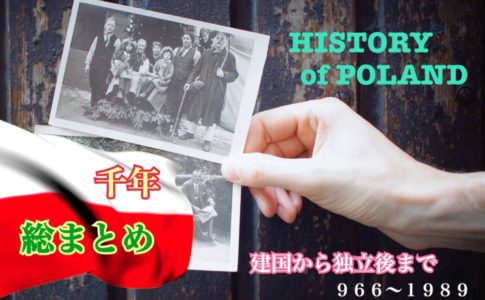


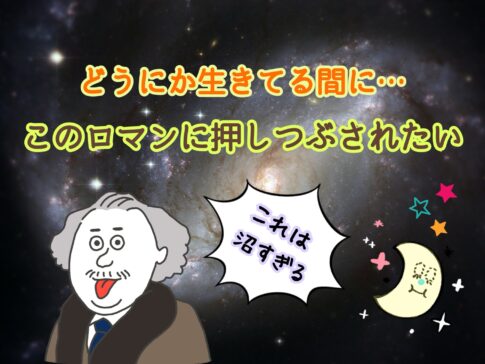




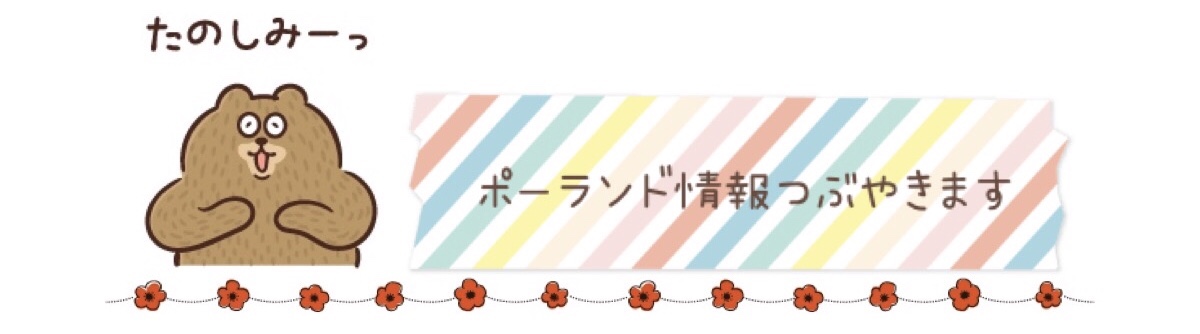
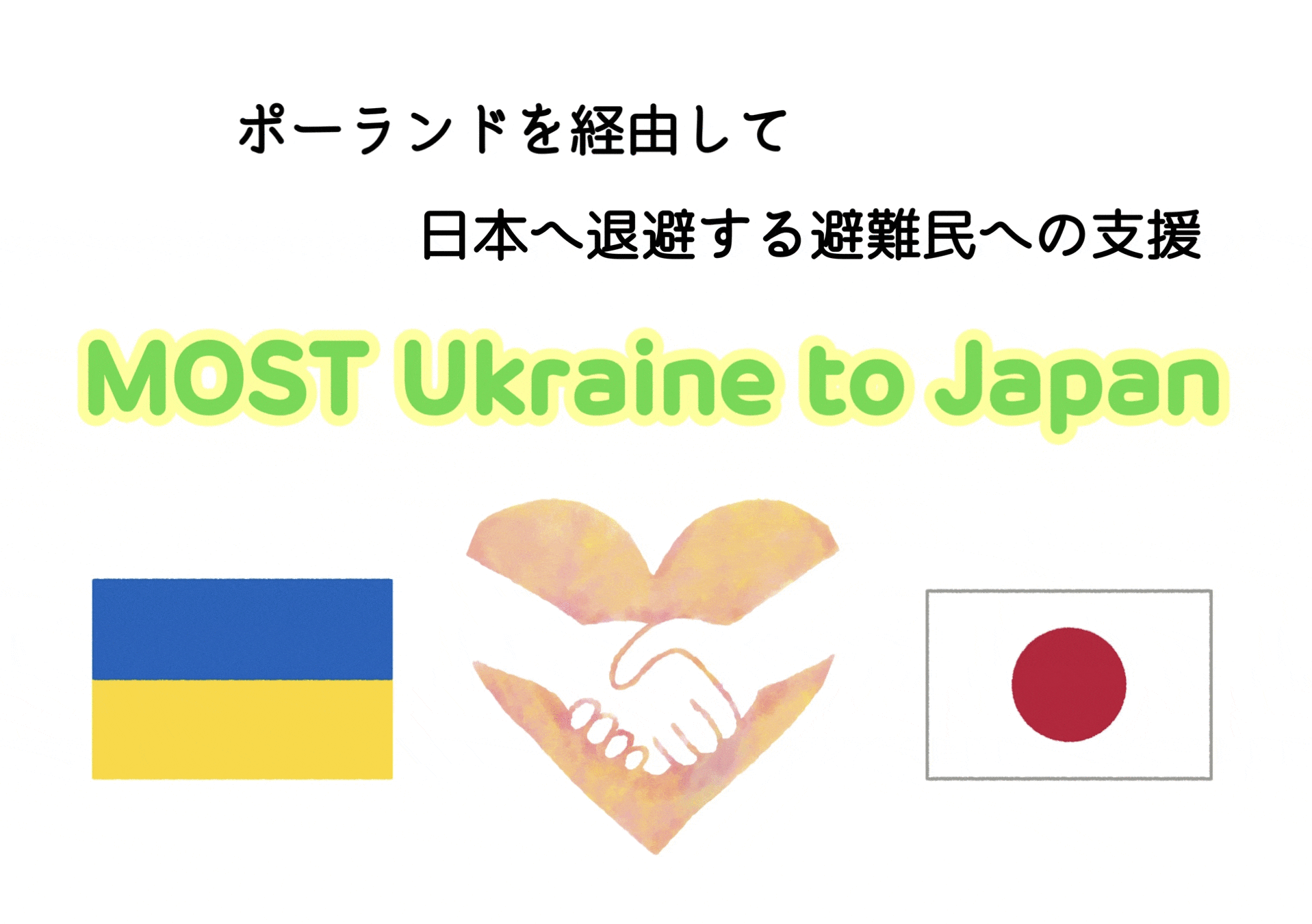










今週の金曜日にアウシュヴィッツに無料入場、土曜日に地下岩塩を予約しようと何度も試しましたが最後のナンバーが間違いと表示されて申し込みできません。どうしたらいいでしょうか?
すみません、どのようなエラーなのか私にも分かりかねます。これまで多くのお客さまに購入をお願いしてきましたが、稀に引っかかるクレジットカードのエラーを除いては皆さまきちんと購入出来ています。直接、問い合わせされたほうがよいかと思います。