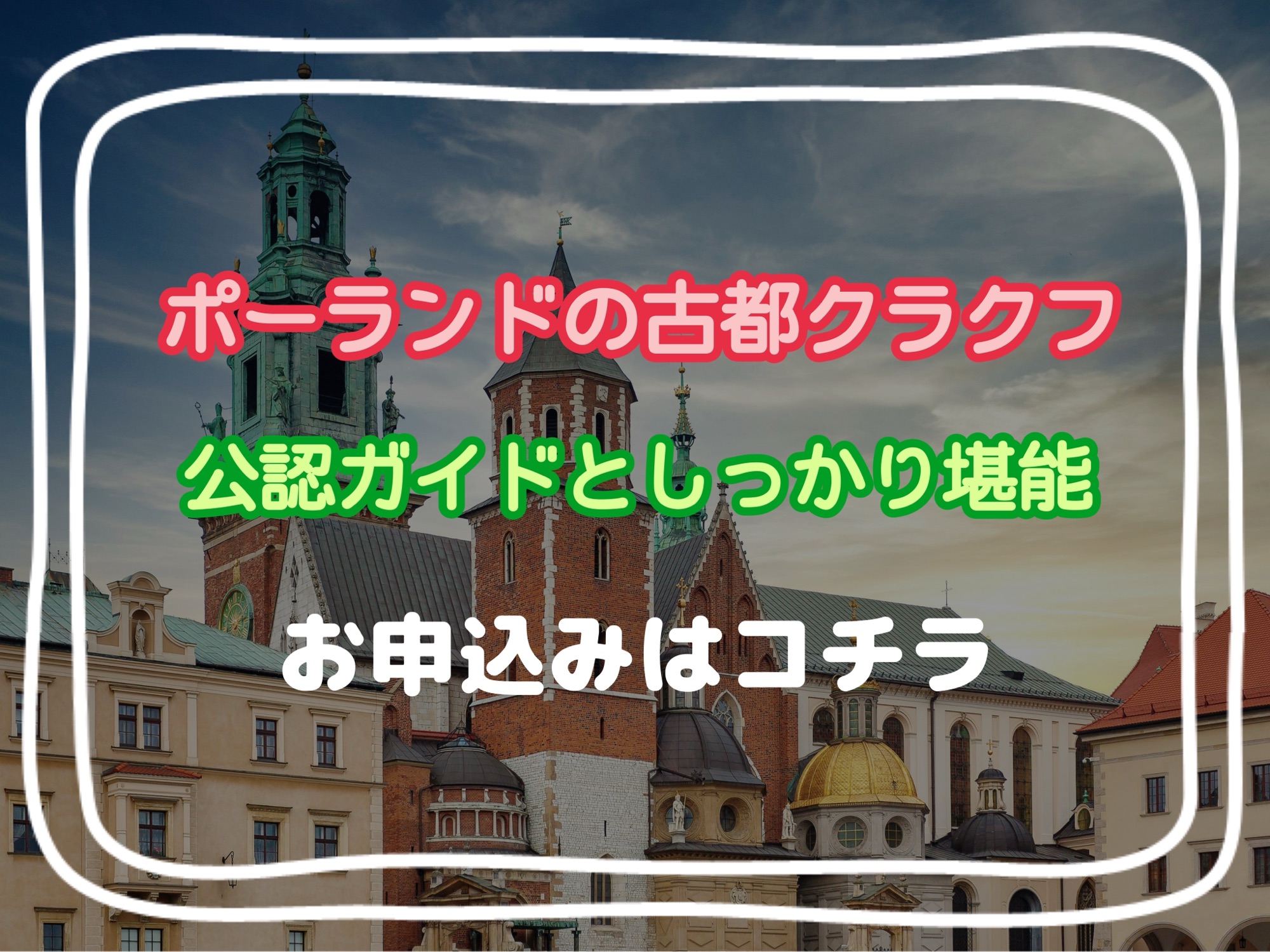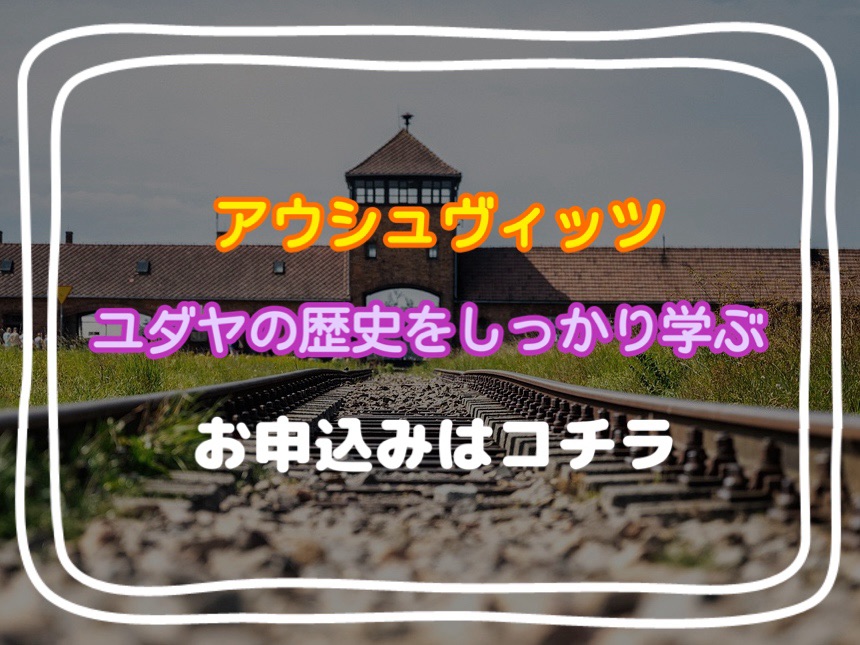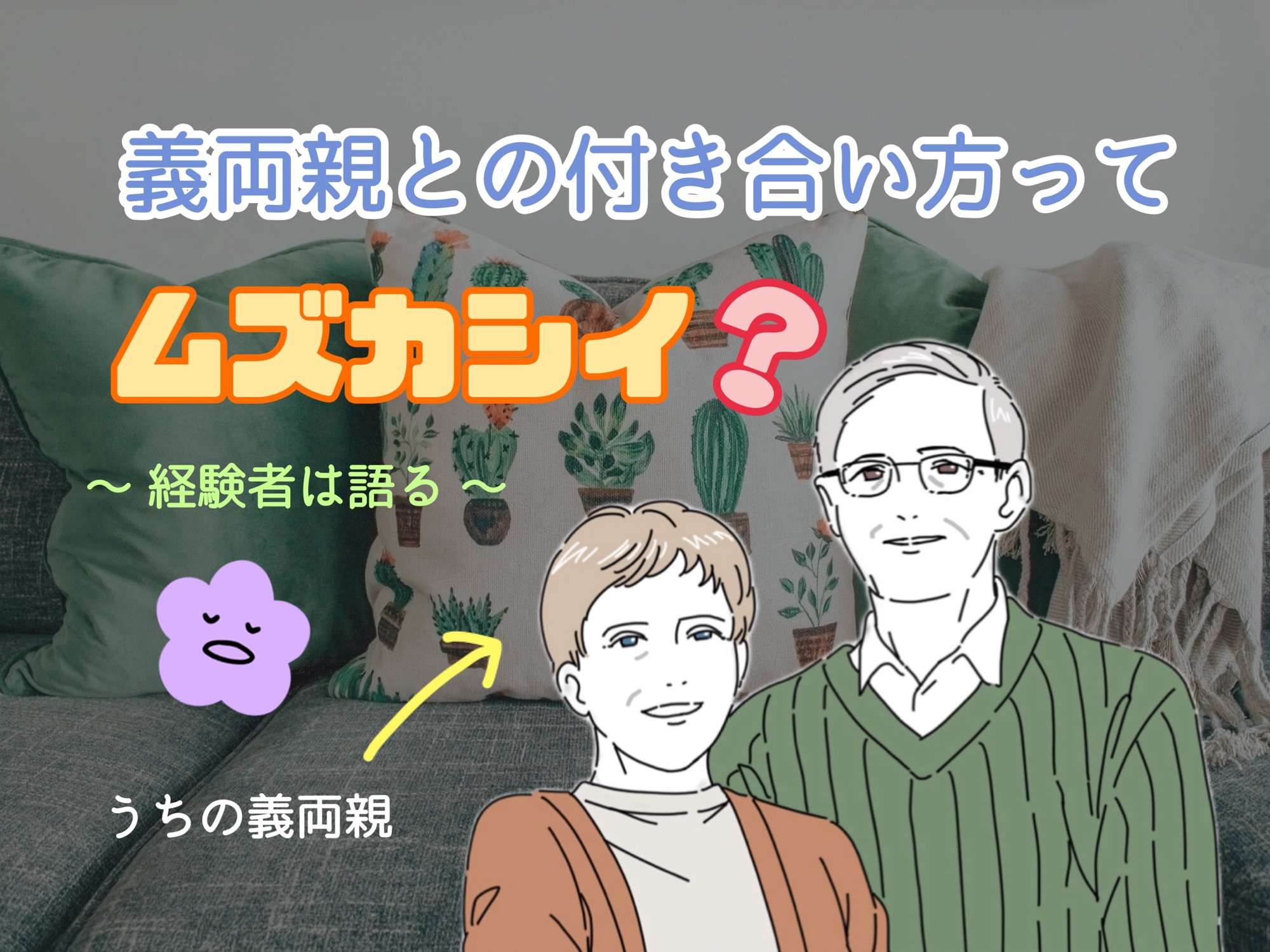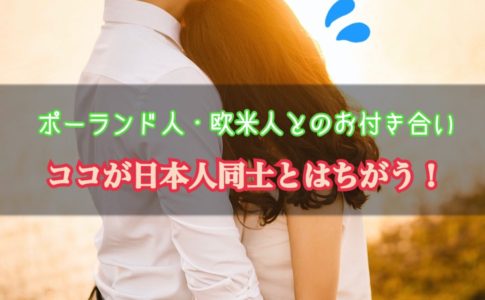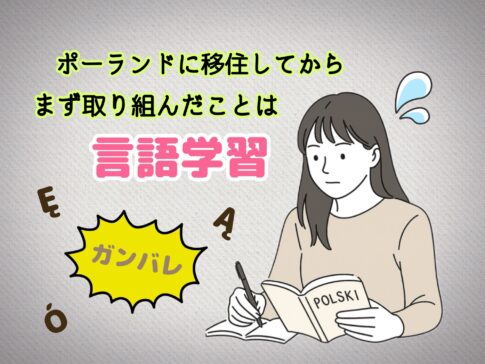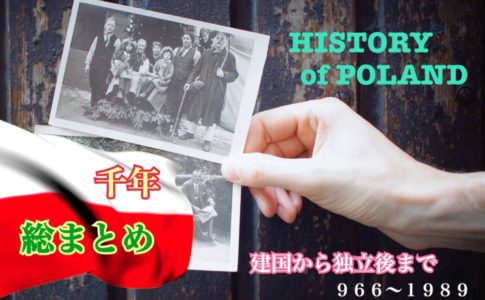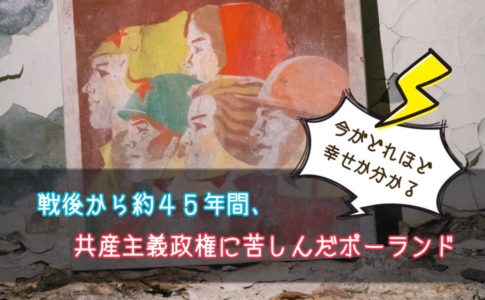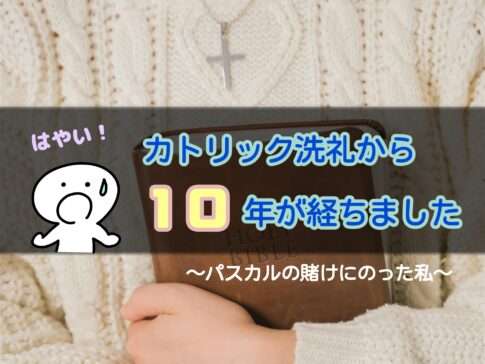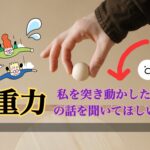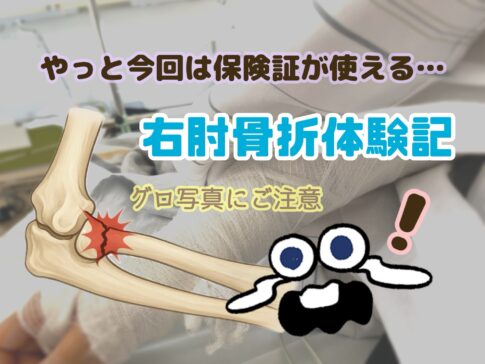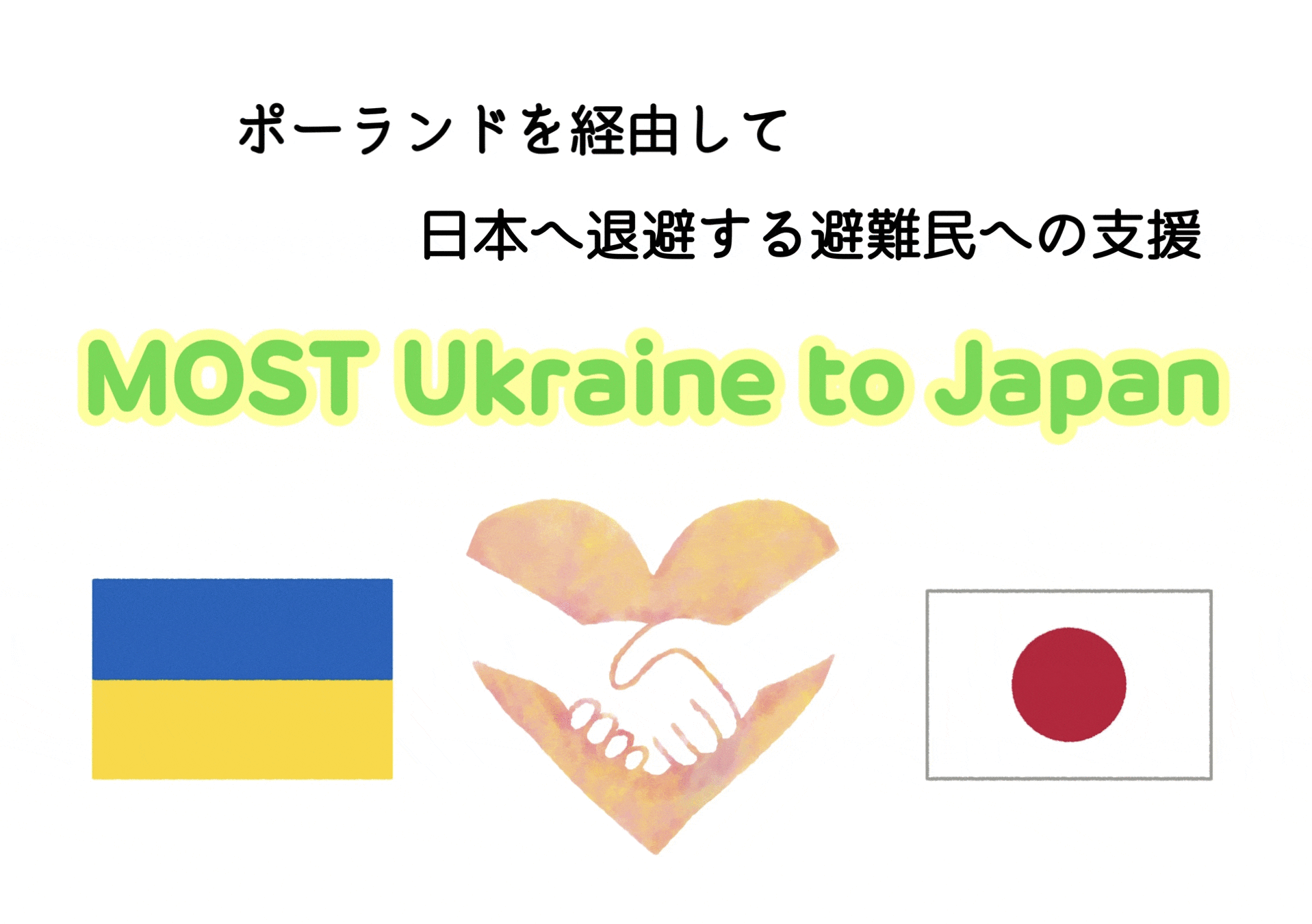◆詳細プロフィールはココ ◆YouTube はじめました
最新記事 by Ayaka (全て見る)
※コンテンツの無断転載禁止(リンク歓迎)
じっくり5分程度で読めます
最近、同じくポーランド人と国際結婚している友人と会ったとき、こちらの義両親との家族付き合いや向き合い方の話になりました。
家族ごとの家庭事情や、個人の性格にも左右されるので【万能な対処方法】はないですが、ある程度の義家族との関係を築いてきた立場から、今一度その経験を振り返ってみたいと思います


国際結婚というと、海外ドラマみたいな愉快な関係(?)を連想する人もいるかもしれませんが、現実にはさまざまな壁があります。そして、ほんの小さなすれ違いが、気づけば大きなストレスに変わっていったりするもの。私自身、今でこそそうした悩みはほとんどありませんが、結婚当初は義両親との同居生活だったこともあり、細かな気遣いや価値観の違いに戸惑うこともありました。今回は、そんな自分の経験を振り返りながら、国際結婚における家族付き合いの難しさ、そしてどう向き合ってきたかについてお話ししたいと思います。
ちなみに、今の義家族との関係は個人的にはとてもうまくいっていると思っています。ただ、それは私が完ぺきだからではなく、むしろ至らない点だらけで、優しい家族にいつも甘えてばかり。心の中では、「本当はどう思われているんだろう…」と不安になることもあります。それでも、ありがたいことにここまで続けてこられました。今年は、私たちにとって結婚10周年、つまり “家族になって10周年” という節目の年でもあります。だからこそ、感謝の気持ちをきちんと伝えたいと思っています
.

1. 言葉の壁を乗り越えるのが最優先
国際結婚の家族付き合いにおいて、最初にぶつかるのが、文化・習慣の違い以上に「言葉の壁」で間違いありません。家族と、自分の言葉で話せないのは、しんどい。当初は日本語が話せるポーランド人の友人たちに助けてもらっていましたが、自分が話せると視野が一気に広がったので、学校サボってでも(←)図書館で勉強した甲斐ありました。ちなみに、私は、例文をひたすら暗記するタイプ。
言語習得ストーリーについては、こちら▼の記事をご覧ください。言語学習に終わりはありません!
.
2. 価値観の裏には相当のワケがある
夫の実家はモノで溢れかえっているわけではないものの、特に、古いオモチャや服はたくさんあります。義両親の若い頃、ポーランドは社会主義国家であり、食べ物や生活必需品は簡単に手に入りませんでした。服はアメリカに逃げた友人から送ってもらっていたのだそう。社会主義を脱したのは1989年ですが、その後も状況的にはまだまだ影響が残っており、とにかく義両親の子育て時代はかなり苦労しているのです。義父が研究者であり教授なので、研究と称して国外へ行く理由を見つけては、西ドイツとかでオモチャを買ってきたのだとか…。
そんな苦しい経験があるからこそ、古くても使えるものは本当に大事にしています。もしこの過去をよく知らなければ、「こんな古いもの捨てればいいのに」と正直思わなくもないですが、そのときの話を聞いてると「そりゃ捨てられないわな」と納得しました。日本でも日本の国ならではの価値観があって、たとえば「米粒は一粒残さず食べる」とかもそうだと思います。確かに、世の中には信じられない価値観もあったりはしますが、価値観の裏にはそれなりの経験と背景があることを理解しておくと受け入れられるようになるかもしれません。
.
3. 宗教は一生をかけて受け入れる
国際結婚を通して強く感じるのは、宗教観の違いが思った以上に日常生活に深く関わってくるということです。私の義家族はみんな敬虔なカトリックで、私も結婚を機にカトリックに改宗しましたが、信仰のかたちは人それぞれ。私はカナダとイギリスに留学していたので、その国々の文化からもキリスト教に抵抗はもともとありませんでした。
たとえば、義姉の夫のきょうだいといった少し離れた親戚には、離婚後に新たなパートナーと暮らしている人もいます。我が家はブラックジョークが好きなので「黒い羊」と茶化していたりはしますが、教義に照らせば複雑な立場といえ、家族はその人を排除せず、自然に関係を続けています。その姿を見て、宗教とは “正しさ” を求めるのではなく、受け入れる寛容さが重要なのだと実感しました。人間だから間違いがあって当たり前。また、信仰は強制されるものではなく、自分で選び、向き合うものだと思います。宗教や価値観の違いは時に壁になりますが、お互いを知ろうとする姿勢こそが、国際結婚において大切な一歩なのだと感じています
.
4. 義家族との無理ない距離感を保つ
ポーランド人は基本的に家族との密接なつながりを大切にしています。しょっちゅう親や子に電話をするし、日曜日や祝日に家に来ないときは「何してるの?」と親から電話がかかってくるし(よそでもアルアルらしい)、休日やイベントのたびに集まるのは当たり前。誕生日や記念日はきちんと祝うし、家族で過ごす時間こそが絆だという価値観が、ごく自然に根づいているのです。さすがにその頻度に少し疲れてしまい、「また〜?」と思ってしまう、そんな自分に罪悪感さえ覚えるほど。
もちろん、これが、彼らなりの「家族を大切にする」という愛情表現なのは百も承知です。彼らにとっては当たり前のあたたかさ。最初はほぼすべて参加していましたが、今では、すべてに合わせる必要はないと思っています。大切なのは、相手の「当たり前」を否定せず、自分自身の心地よさもきちんと尊重すること。そう思えるようになってからは、ずいぶんと気持ちがスッキリ楽になりました。
.
5. 家族チャットで無理なく繋がる
最近ようやく家族のグループチャットに加わったのですが、「もっと早く入ればよかった」と思うほど、家族との距離がまた一気に縮まりました。リアルで集まると、人が多すぎて話題が飛んだり、伝えたいことが埋もれてしまうこともあるのですが、チャットなら全員が落ち着いて内容を読めるので、言葉も気持ちもスムーズに届きます。
たとえば先日、結婚10周年の記念に義姉夫婦がお皿をプレゼントしてくれたのですが、それをさっそく使っている写真をグループチャットに送ったら、とても喜んでもらえました。ちょっとしたことでも「受け取ったよ」「嬉しかったよ」と伝えることで、気持ちが通じ合えるのを実感。ただ一方で、人によってはそこまで密な関係を求めていない場合もあるし、グループに入ることで距離が近くなりすぎて疲れると感じることもあると思います。だからこそ、自分にとって無理のない関わり方を選びながら、オンラインならではのゆるやかで心地よいつながりを大切にしていきたいと思っています。
.
.
6. 言葉の裏にあるのは、いつも愛情
義両親は5人の子どもを育て上げ、今では10人の孫がいる大ベテラン。そんな二人から子育てについて何か言われたとしても(あまり何も言ってこないけど)、「おっしゃる通り」としか言えない説得力があります。よく、娘や私に対して「ちょっとちょっと、薄着すぎない?帽子は?マフラーは?」と指摘してきますが、それも心配してくれているからこそ。嫌味なアドバイスではありません。
どこのママも「私はこうして育ててきた、育てられた」という自信と愛情があると思います。確かに、時代も変わり、子育ての常識も子どもへの医療も変化しています。でも、私たちが自分のクセをなかなか変えられないのと同じように、向こうもそう簡単には考えを変えないでしょう。どちらが良い悪いではなく、度が過ぎない限りは「前提が違うだけなのだ」と思うしかありません。育児スタイルは日本人でも千差万別であり、文化だけでなく、家庭ごとの経験も大きく影響しているのだと感じます。
.
.
.
 国際結婚は言葉や文化の違いというハードルがある反面、だからこそ築ける新しい家族の形があります。すぐに仲良くなる必要も、無理にすべて理解し合う必要もありません。と、今は俯瞰して語れますが、本当にこれは家庭それぞれなのでココに書いたことが一般論とは思わないです。私は義両親を尊敬していますが、ちょっと変わった考えを持つ人がいるのも事実。あくまで個人のケースとして読んでもらえたのなら嬉しいです!
国際結婚は言葉や文化の違いというハードルがある反面、だからこそ築ける新しい家族の形があります。すぐに仲良くなる必要も、無理にすべて理解し合う必要もありません。と、今は俯瞰して語れますが、本当にこれは家庭それぞれなのでココに書いたことが一般論とは思わないです。私は義両親を尊敬していますが、ちょっと変わった考えを持つ人がいるのも事実。あくまで個人のケースとして読んでもらえたのなら嬉しいです!