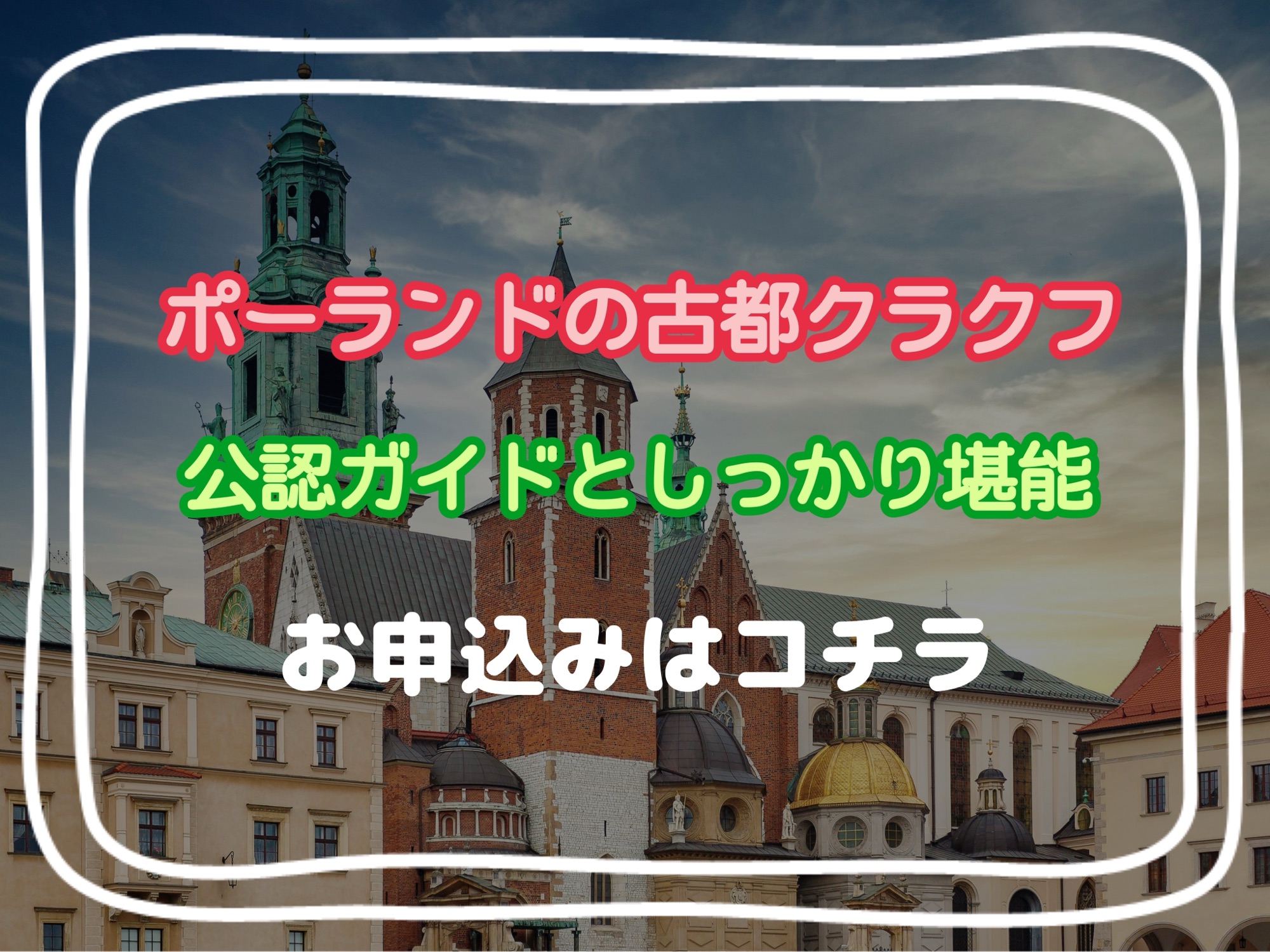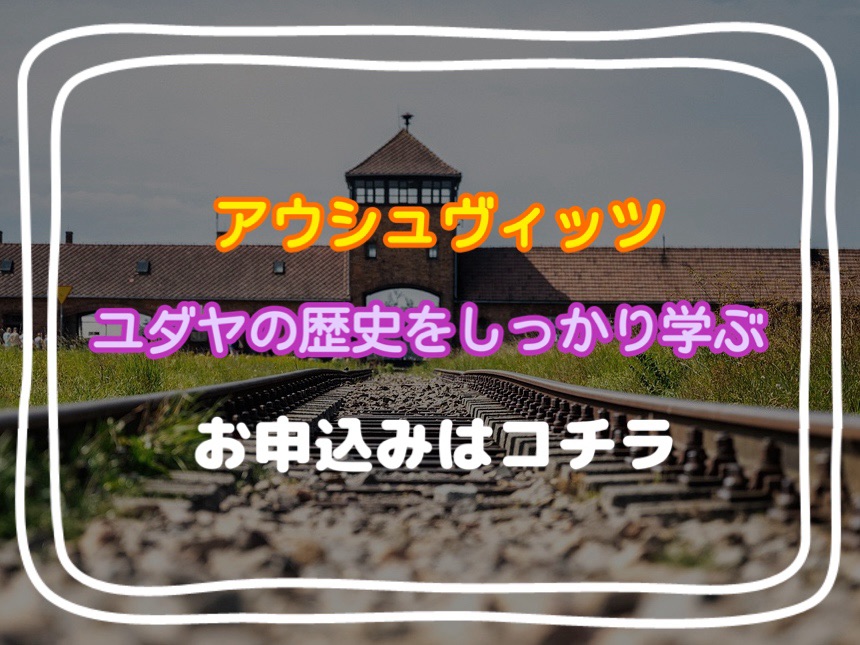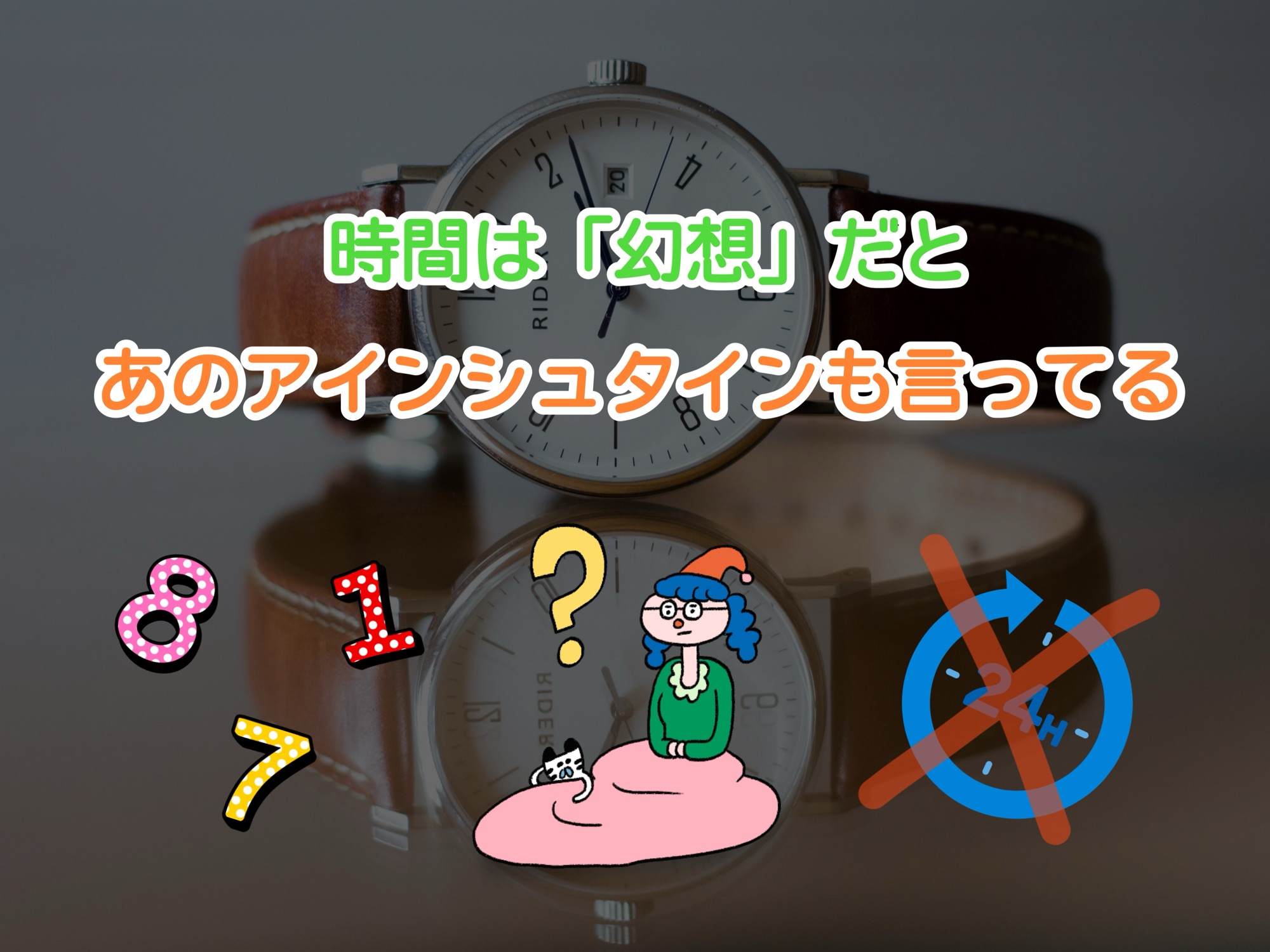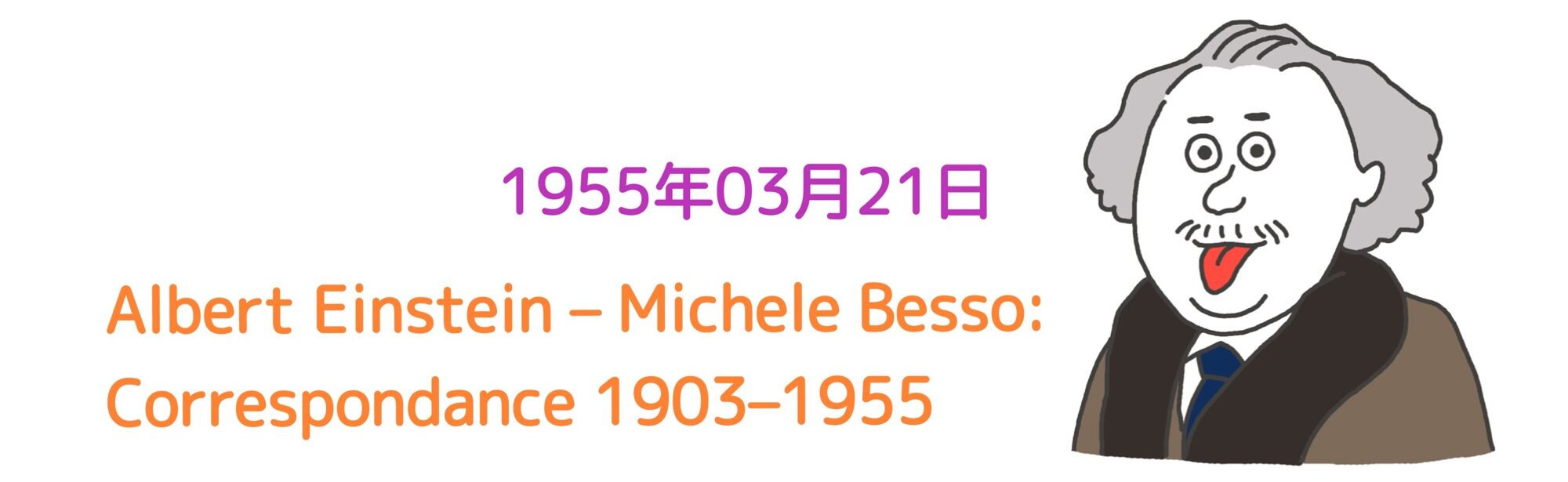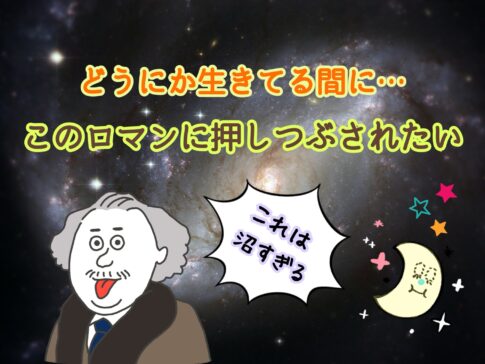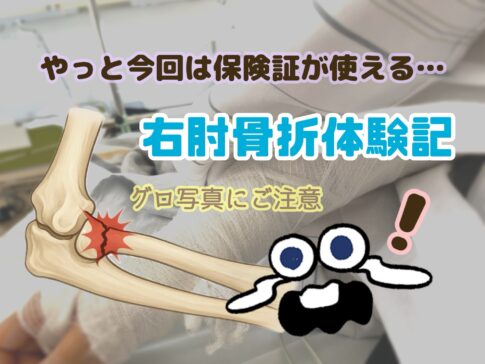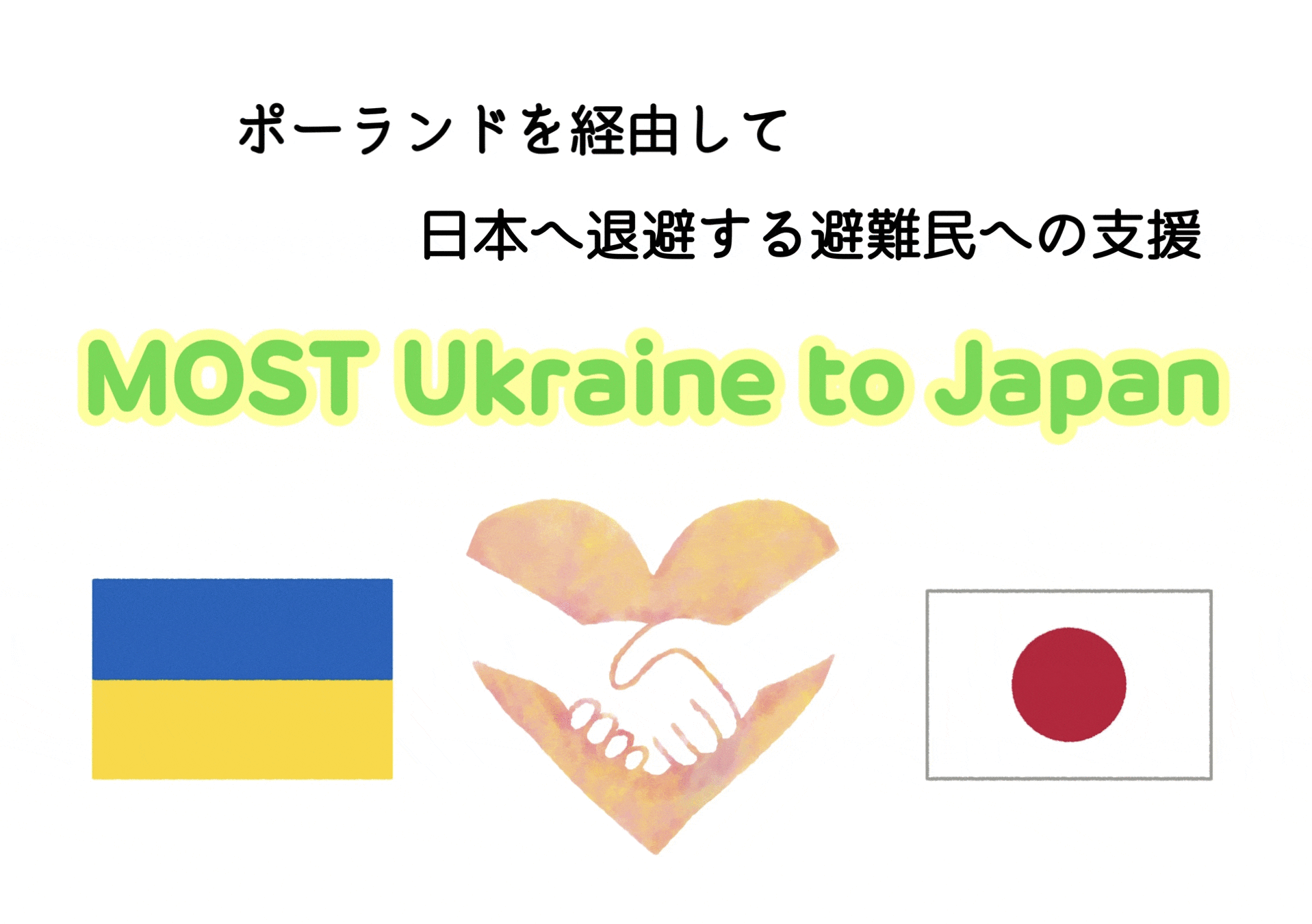◆詳細プロフィールはココ ◆YouTube はじめました
最新記事 by Ayaka (全て見る)
※コンテンツの無断転載禁止(リンク歓迎)
この動画で話されている内容、かなり興味深い!
物理的にも本質を突いてます。しかし、この未来人が100年先からやって来たという点だけはどうしても信じられない…。それほど間隔が空いたら、日本人同士でもスムーズに会話できないのでは?
でもこういう話、昔からめちゃくちゃ好きです
.

私にとって、この未来人・塚本の言う「我々は時間を共有しているだけで、それぞれは別の時空に生きている」「過去や未来は同時に存在する」みたいな考えは結構しっくり来ます。
私たちの意識が「いま」という一点に集中しているから「過去」や「未来」という感覚が生まれるのであって、本来、時間は区別できないもの。
アインシュタインは物理学者の友人ベッソが亡くなったとき、こんな言葉を残しました。
.
彼は、我々よりも少しだけ早く次の部屋へ行っただけだ。我々物理学者にとって、過去・現在・未来の区別はただの幻想に過ぎないー。
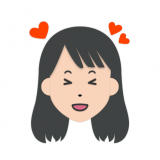
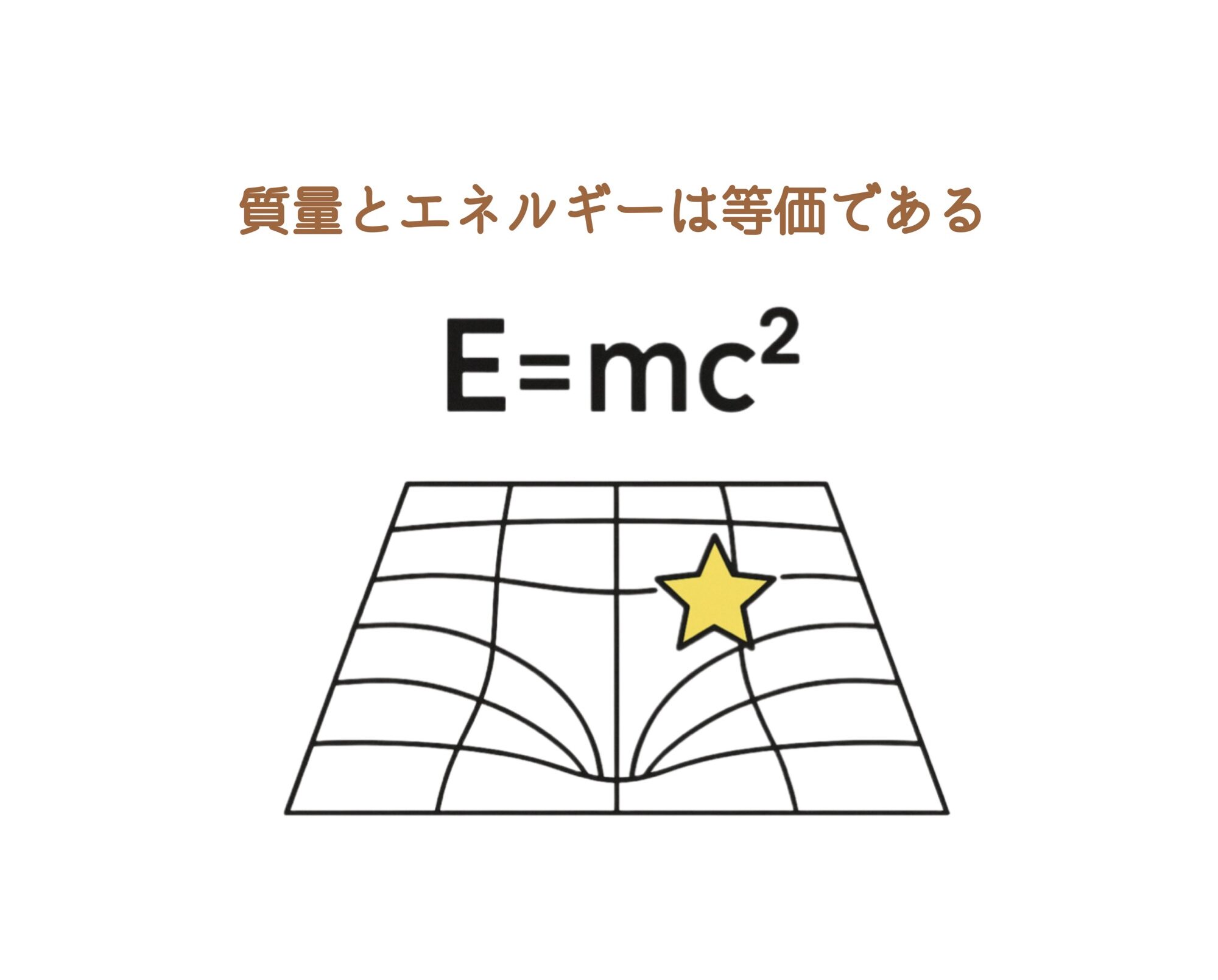
「E = mc²」が示したように、宇宙においてはエネルギーと質量が同じものであり、時間もまた絶対的なものではないとアインシュタインは考えました。この宇宙の根本法則は彼の人生観や死生観にも深く影響しており、この考え方を通して、死をも「絶対ではないもの」と捉えることができるのです。
.
.
物体が高速で動くと時間は遅くなり(特殊相対性理論)、重力の弱い山頂のほうが地上よりも時間は速く進む(一般相対性理論)という事実からも、時間は絶対的なものではありません。
とある観点からすれば、「死」は時間という構造の中の、別の場所への移動に過ぎないのです。
こんなことを書いてると、「だれか大切な人を亡くしたの?」と思われそうですが、昔から離人感を抱きながら生きてるので… ふつう。
ストレスがあるとそういう思考になるらしいんですが、生まれつきの感覚と言ってもいいです。
ふと自分を見たとき、本当の自分ではない仮の姿のように感じることってないですか?
生まれた瞬間から大きな流れに乗せられ、親に育てられ、学び、働き、家庭を持ち、死へ向かっていくー。だれに強制されたわけでもない時間を過ごし、当然かのようにみんな繰り返してる…。
自分で選んできたような人生で、実は初めから仕組まれているような、ある種の既視感。

何を食べるか、何を買うか、だれと会うか、毎日の選択は確かにあるけど、生まれた場所や育ってきた環境、幼い頃に身につけた価値観などは完全に自分が決めたことではありません。
与えられたものであって、そのスタート地点の差が、すでに人生の方向を大きく決めています。
表面的にはみんな同じ時間を生きているように見えるけど、実際には「裕福な家庭に生まれた若者の時間」と「働かざるを得ない若者の生きるための時間」は違うし、病気や差別、社会的立場によって自由な時間は削られていきます。
不平等なのは時間そのものではなく、その時間の中で何が出来るか、どう過ごせるかという余白の格差であって、クエストみたいなものですね。
自分が恵まれていると感じるなら、その恵みを分けよう、と行動を起こせる人になりたい。
肩書きや社会的立場、経済的な余裕さに優越感を抱く人があまりにも多すぎる世の中。
だれかのためではなく、ただ世界に触れたくて探求する人、認められるかも分からないようなことを一生追い求めているような、そんな関孝和みたいな人生を歩む人とお近づきになりたいなぁ。
1. 時間の不思議な流れ、時間は幻想?
アインシュタインは、過去・現在・未来という区別は、「ただの幻想だ」と言いました。つまり、私たちが常に感じる時間の流れ、それは私たちの意識が作り出したものに過ぎないのです。
例えば、あなたが川を見ているとしましょう。その川はずっと流れつづけていて、時間もそのように「流れていくもの」と感じますよね。でも物理学的に見ると、その流れていく川は、私たちが見ている一部分に過ぎません。時空という広がりの中で、過去も未来も実はすでに「そこに存在している」というように考えると、時間が流れるのではなく、私たちがその中を進んでいるだけだとも言えます。
2. 量子力学と時間の不確かさ
量子力学的観点では、「物事が確実に決まっていない」という面白い現象が起こります。
例えば、物質の最小の部分である量子は、原理的にどこにあるかがわからないんです。確率の中にあって、その確率分布を計算するための式がシュレディンガー方程式。粒子の位置や動きが決まっていないなら、時間の流れも決まっていないようなもの。もし量子力学の考え方を時間にも当てはめると、時間も量子化されているかもしれません。つまり、時間はとても小さな単位で区切られているかもしれなくて、私たちが感じる「時間の流れ」は、その小さな単位で飛び跳ねているような感じなのかも。そう考えると、時間が滑らかに流れているように感じるのは、ちょっとした勘違いの可能性があります。
3. エントロピーは無秩序の度合い
エントロピーとは、簡単に言うと、物事がどれだけ乱れているかを示すもの。例えば、温かいコーヒーが冷めるとき、コーヒーの中の熱が外に広がっていきますよね。これがエントロピーが増えるってことです。エントロピーが増えるということは、時間が進んでいる証拠でもあり、これこそ私たちが「時間が流れている」と感じる理由なんです。
もしエントロピーが最大になったらどうなるかというと、全てが無秩序で均一な状態になり、時間が止まったように感じるかもしれません。これを「熱的死」と呼びます。怖い未来かもしれませんが、物理学的には一つの可能性として存在しています。
4. 時間の流れはどうして一方向?
物理学では、「時間の矢」と呼ばれるものがあります。これは、時間が「過去から未来へと進む」方向性を持っているという現象です。時間が一方向に進む理由、それはエントロピーが増えるから。過去と未来が区別できるのは、エントロピーの増加という「時間の矢」があるからなんです。
でも、量子力学では、時間が逆に進む可能性もあると言われています。小さな粒子の世界では、時間が前後に動くことが理論的には起こり得るのです。でも、私たちの普段の生活では、時間は逆行しません。それは、エントロピーがとても低い確率でしか逆転しないから。どれくらい低い確率かと言うと、砂漠の砂が一粒ずつ空を飛んで、それがまた元の砂山に戻るくらいとでも言いましょうか。
5. おまけ:実際に計算してみよう
特殊相対性理論における時間の遅れを求める基本式は【Δt’ = Δt * √(1 – v² / c²)】です。
Δt は静止している観測者にとっての時間、Δt’ は高速で移動する観測者にとっての体感時間、v は物体の速度、c は光速(約 3.0 × 10⁸ m/s)。例えば、約4.37光年先のアルファケンタウリへ行く場合、宇宙船が光速の90%(v=0.9c)で移動すると、地球から見た所要時間は【Δt = 距離 / 速度 = 4.37 / 0.9 ≈ 4.86年】(途中式略)となり、宇宙船に乗っている人の体感時間は【Δt’ = 4.86 * √(1 – 0.9²)= 4.86 * √(1 – 0.81) ≈ 2.12年】になります。つまり、高速で動くほど時間が短く感じられるというのが分かります(遅く進むということ)。